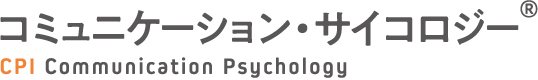子どもが不登校になる原因は?親ができる最善の対応を紹介!
2025.07.12

子どもが不登校になる原因は?親ができる最善の対応を紹介!
不登校になってしまう子どもは年々増加しています。
これは、社会的にも大きな問題となっていますが、家庭内においても重大な問題といえます。
子どもが不登校になってしまうことを防いだり、不登校の子どもに対して心のケアを行ったりするためには、正しい知識を身につけておくことが大切です。
そこでこの記事では、子どもが不登校になる原因や、親ができる最善の対応について詳しく解説していきます。
《目次》
1.子どもが不登校になる原因として考えられること
2.子どもの心を開くために親ができることは?
3.不登校の子どもに対して親が絶対にやってはいけないこと
4.まとめ
1. 子どもが不登校になる原因として考えられること
子どもが不登校になってしまうのには、様々な原因があります。
その中でも特に多いのが、以下4つです。
・学校でのトラブル
・親とのコミュニケーション不足
・非行
・学業不振
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
学校でのトラブル
子どもが不登校になってしまう原因として最も代表的なのが、学校でのトラブルです。
いじめはもちろん、教師との関係性など様々なことが考えられます。
学校でのトラブルを放置すると、子どもの命を危険にさらすほど大きな問題に発展してしまうことがありますので注意しましょう。
その他、集団生活に適応するストレスなど、他者に原因がないケースもあります。
親とのコミュニケーション不足
親とのコミュニケーションは、子どもにとって非常に重要です。
しっかりとコミュニケーションが取れていれば、子どもの心の健康を保てるようになるため、不登校になるリスクを下げられます。
一方で、親とのコミュニケーションがほとんどない場合や、家庭内で問題が起こっている場合などは、子どもの心理的健康が損なわれるため、結果として不登校に繋がる可能性が高くなります。
非行
非行や遊びによって不登校になってしまう子どもも少なくありません。
子どもが非行に走る原因は1つではありませんが、家庭内での問題や、付き合う友人の影響などが原因となるケースが多いです。
子どもの非行を見て見ぬふりすると、周囲に迷惑をかけたり、子ども自身の心に深い傷を負わせてしまったりする可能性が高くなりますので注意しましょう。
学業不振
「勉強がうまくいかない」
という理由で不登校になってしまう子も比較的多くいます。
学業不振で不登校になってしまう子どもは、真面目で勤勉なことが多いです。
それ自体は素晴らしいことですが、ときとして自分自身の首を絞めることもあります。
また、親からのプレッシャーによって嫌々勉強をしているケースもありますので、教育方針やコミュニケーションの取り方を工夫していかなければなりません。
2. 子どもの心を開くために親ができることは?
子どもが不登校になってしまうのを防ぐためには、子どもと上手にコミュニケーションを取ることが大切です。
以下のポイントを意識することによって、子どもと良好な関係を築きやすくなります。
・子どもの気持ちをしっかり受け止める
・絶対に否定しない
・ゲームやタブレットは時間を決める
・子どもに役割を与える
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
子どもの気持ちをしっかり受け止める
子どもが学校に行きたがらない場合は、ひとまず子どもの話を最後まで聞き、気持ちをしっかり受け止めることが大切です。
・何が嫌なのか
・どうすれば学校に行けるようになるのか
・両親にどんなことをしてほしいのか
といったことをしっかり話し合い、子どもの気持ちを理解することが、不登校の防止や解消に繋がります。
絶対に否定しない
子どもが不登校気味になっていたり、学校に行くことを拒否していたりしても、頭ごなしに否定してはいけません。
中には、
「子どもは学校に行くのが仕事だ」
「とにかく学校に行きなさい」
と理由も聞かずに反論してしまう方もいますが、これは逆効果です。
「親は自分の話を聞いてくれない」と子どもが失望してしまい、さらに心を閉ざす可能性も高くなりますので注意してください。
ゲームやタブレットは時間を決める
デジタル化が進んでいる昨今においては、ゲームやタブレット、パソコンなど子どもにとって多くの誘惑がある端末が増えています。
非常に便利で楽しい道具ですが、使い方を間違えると子どもの気力ややる気を奪ってしまいます。
子どもは自制心が若干弱い傾向にあるため、ある程度の年齢までは両親がしっかり見守ってあげることが大切です。
時間を決めたり、ルールを決めたりすることにより、メリハリのある生活を送れるようになるため、不登校を防ぎやすくなります。
子どもに役割を与える
子どもが不登校気味になっている場合は、役割を与えてあげましょう。
というのも、学校に行きたがらない子どもの中には、自分の居場所がないと感じてしまっている子もいます。
学校はもちろん、家でも孤独を感じてしまっているケースがありますので、役割を与えて「ここは自分の居場所である」と感じてもらうことが大切なのです。
3. 不登校の子どもに対して親が絶対にやってはいけないこと
我が子が不登校になってしまった場合、どうすればいいかわからなくなってしまうでしょう。
子どもによってアプローチの方法が変わるため、一概に正解をお伝えすることはできませんが、以下の行動は絶対に避けるべきです。
・無理やり部屋から出そうとする
・一方的に叱る
・放任する
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
無理やり部屋から出そうとする
自分の部屋から出てこなくなってしまった場合、きっとお父さんやお母さんもパニックになってしまうと思います。
中には、現実を受け止めきれず、無理やり部屋から出そうとしてしまう方もいると思いますが、この行動は絶対にNGです。
部屋から出たがらないのには、何らかの原因があり、それを解消できない限りは不登校や引きこもり問題を解消することはできません。
無理に部屋から出したとしても、すぐにまた自分の殻に閉じこもってしまいますので、問題の根本解決に向けて動き出しましょう。
一方的に叱る
子どもが学校に行かないことに対して、一方的に叱るのは間違っています。
なぜなら、子どもには子どもの感じ方があり、学校に行きたくないのにも必ず理由があるからです
これらを聞き出すこともなく一方的に叱るのは、親のエゴだといえます。
先ほども解説したように、子どもが不登校あるいは引きこもりになるのには、必ず理由がありますので、まずは子どもとしっかりと話し合い、原因を解明するところからスタートしましょう。
放任する
不登校あるいは学校を嫌がる子どもとの向き合い方で悩み、最終的にどうすることもできなくなって放任してしまう方が一定数います。
しかし、親が諦めた瞬間に、子どもが心を完全に閉ざしてしまいます。
そうなれば、子どもの心に大きな傷を作ってしまうことになり、状況が悪化する可能性がありますので、どうすれば我が子が元の生活に戻れるのか、学校に行きたがるようになってくれるのかを考えつつ、しっかりと向き合っていきましょう。
4. まとめ
子どもが不登校になってしまうのには、必ず原因があります。
万が一子どもが不登校になってしまった場合は、ひとまず原因を確認し、子どもと一緒に対応を考えていくことが大切です。
また、不登校の子どもに対して、絶対にやってはいけないこともいくつか存在しています。
今回紹介した間違った対応をしてしまうと、子どもが完全に心を閉ざし、状況が悪化してしまう可能性が高まりますので注意してください。
——————————————————————————————————————————–
CPIでは、コミュニケーションのスペシャリスト育成講座、堀口メソッド エグゼクティブ・コーチング、子育てCOACHなどの各種講座を開催しております。
★体験会随時開催中 詳細はこちらから★
NLPコミュニケーション・サイコロジー体験会